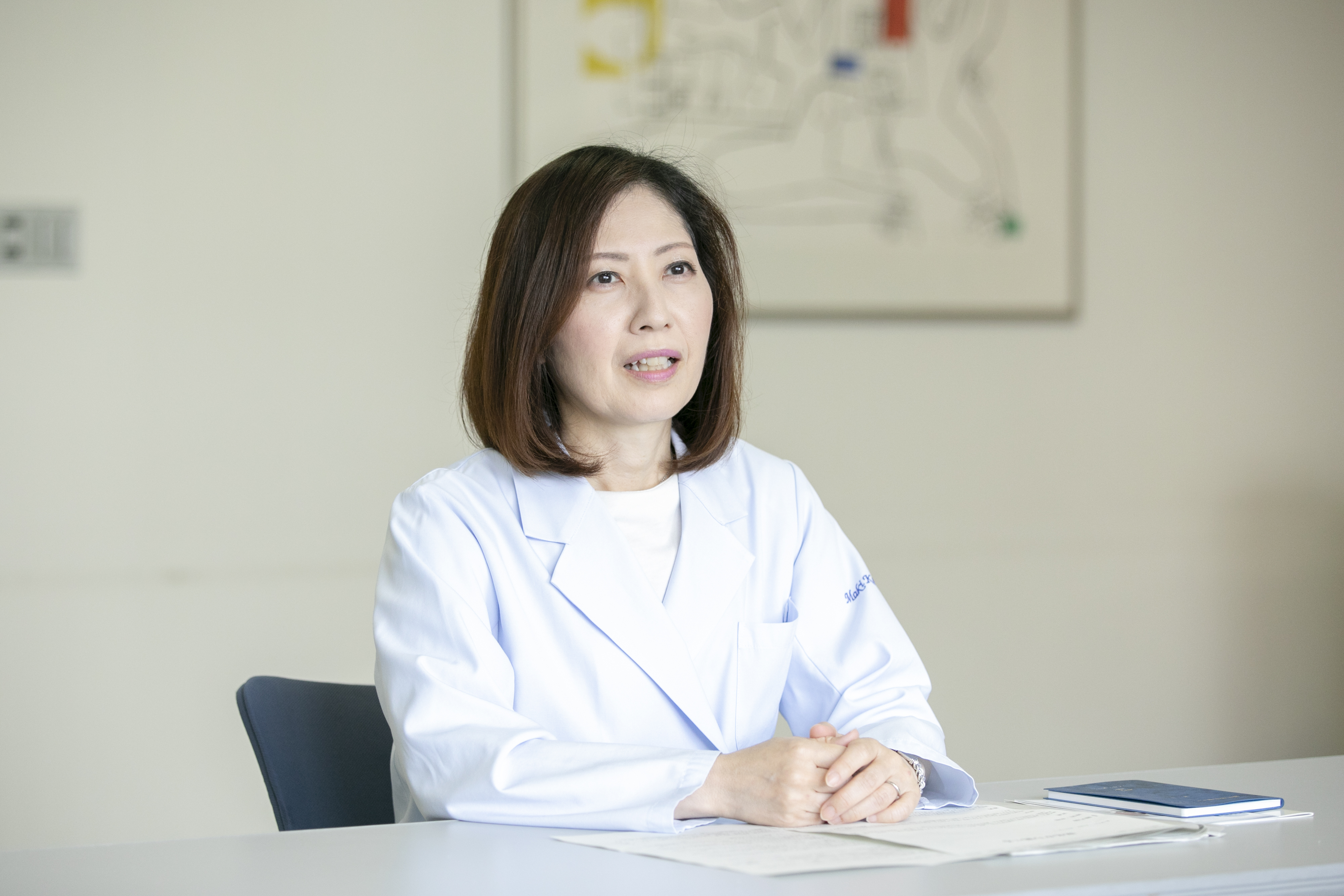DOCTOR INTERVIEWドクターインタビュー
- トップページ
- ドクターインタビュー
- 眼科ドクターインタビュー
患者と医療者、
治療は⼆⼈三脚。

眼科部長 片井 麻貴
総合病院の眼科として、希少疾患・難治例に対応する⾼度な専⾨性を有しながら、新⽣児から⾼齢者までが頼れる地域の“かかりつけ眼科”としての役割も果たし、常に患者の⽴場に⽴った思いやりある医療を提供しています。
同科の取り組みや⽇々の診療の思い、⾼齢社会の進展に伴い増加する眼疾患、失明原因の第 1 位である緑内障の症状や治療法など、⽇本眼科学会認定眼科専⾨医の⽚井⿇貴眼科部⻑にお話を伺いました。
どういった診療を⾏なっていますか?
眼科領域全般について⽇本眼科学会眼科専⾨医 3 名で診療にあたっています。総合病院の眼科として、全⾝疾患のある患者さんも数多く診ており、糖尿病、⾼⾎圧症、膠原病、ウイルス感染症など全⾝疾患に伴う眼合併症の管理、副腎⽪質ステロイド薬や抗がん剤を使った治療における眼副作⽤のチェックなどを、糖尿病内分泌内科や循環器内科、呼吸器内科、消化器内科、腎臓内科、リウマチ膠原病内科、外科、産婦⼈科、⼩児科など他診療科と密接に連携しながら⾏なっているのが特⾊です。
新⽣児、⼩児から⾼齢者まで、扱う眼疾患は多岐にわたります。希少疾患、難治例の治療に携わることも少なくありません。私たちを頼って受診される患者さんのために、私たちは学び続けなければなりません。学会や研究会・研修会に積極的に参加し、⽇々知識・技術の向上に努め、科学的根拠に基づく最新の眼科医療の提供を⽬指しています。
どういうことを⼼掛けて診療にあたっていますか?
眼科に限りませんが、医療は患者さんと医師との⼼の交流、信頼関係の上に成り⽴つものだと思っています。「病気」だけでなく、その「⼈」を⾒つめ、患者さんとしっかり向き合い、患者さんといっしょに病気に⽴ち向かっていくこと。「患者さんを診る」が、私の信念です。患者さんが持つ考え⽅や感情、⽣活や仕事、家族や友⼈との関係、そういった社会的背景を理解したうえで、治療⽅針を決定し、患者さんの眼の困り事を解決するよう導いていくのが私たちの役割だと考えています。
どのような患者さんが多いですか?
眼の痛みや渇き、違和感のほか、「⾒えにくい」「⾒えない部分がある」など患者さんの訴えは多彩ですが、⾼齢社会の進展に伴い、加齢によって起こる眼の病気が増加傾向にあります。頻度の⾼い疾患は、緑内障、⽩内障、糖尿病網膜症、加齢⻩斑変性などです。眼をカメラに例えたときレンズにあたる⽔晶体が濁って光が通りにくくなり、ものが⾒えにくくなるのが⽩内障です。早い⼈では40代から、80代ではほぼ全員が⽩内障になります。治療には点眼薬を使う場合もありますが、進⾏を遅らせるだけで、弱った視⼒を回復させる効果はありません。このため、⽣活に不⾃由を感じるようになったら、濁った⽔晶体を取り出し、眼内レンズに⼊れ替える⼿術を⾏います。⼿術をすれば、多くのケースで⾒え⽅の回復が期待できます。
⽇本⼈の中途失明原因第 2 位の糖尿病網膜症。⾎糖値の⾼い状態が続くと網膜の細い⾎管が詰まったり破れたりします。⾎管が詰まると網膜が酸⽋状態に陥り、その結果として新たにできる異常な⾎管(新⽣⾎管)が破れて出⾎したり、網膜剥離を起こしたりします。治療は、⾎糖のコントロールを基本に、病状によってレーザー治療やステロイド剤、抗VEGF(⾎管内⽪増殖因⼦)薬の投与、硝⼦体⼿術などが検討されます。加齢⻩斑変性は、年齢を重ねるとともに網膜⾊素上⽪の下に⽼廃物が蓄積し、網膜の中⼼である⻩斑部の働きが低下します。ものがゆがんで⾒える、ぼやけて⾒える、中⼼が暗く⾒えるなどの症状があらわれます。滲出型と萎縮型の 2 種類があり、⽇本⼈の多くは滲出型で、放置していると失明のリスクが⼤きいのもこのタイプです。新⽣⾎管が悪化の原因なので抗VEGF薬の硝⼦体注射やレーザーによる治療法があります。そして、⽇本⼈の中途失明で最も多いのが緑内障です。40歳以上の20⼈に1⼈が何らかのタイプの緑内障であるとみられるのに、約 9 割の⼈が緑内障であることに気付いていません。
緑内障とはどのような病気ですか?
緑内障は、眼圧の上昇などにより眼と脳をつなぐ視神経が傷害され、視野が⽋けてしまう(⾒える範囲が狭くなる)病気です。⼀度失われた視神経を元に戻すことはできません。視神経がどれくらいの眼圧に耐えられるかは個⼈差が⼤きく、中でも⽇本⼈では眼圧が正常範囲であっても障害が進⾏するケース(正常眼圧緑内障)が多いことが分かっています。
初期から中期にかけては⾃覚症状がほとんどありません。普段、私たちは両眼を使ってものを⾒ています。⽚⽅の眼に異常があらわれた場合でも、もう⼀⽅の眼が無意識にカバーするので、少しずつ視野が⽋けてきても気が付きにくいです。そのため、⾒えづらさを⾃覚したときにはすでに⼿遅れとなってしまっている場合が多く、これが緑内障の最も怖いところです。
何よりも重要なのが、早期発⾒・早期治療です。⾃覚症状が出る前に⾒つけることで、眼の機能に影響が出ないよう病気の進⾏を⾷い⽌めることができます。⼀般的な健康診断で緑内障の検査は眼圧測定、眼底写真撮影とされていますが、中でも正常眼圧緑内障は眼圧検査だけでは発⾒できないため、確実に診断するためには眼科で網膜などの状態を調べる「眼底検査」、⾒える範囲をチェックする「視野検査」などを受ける必要があります。
緑内障の治療について教えてください
緑内障の治療は、緑内障になった眼の進⾏を遅らせるために、その眼にとってのバランスの良い「⽬標眼圧」を⽬指して、眼圧を下げることです。視神経を回復させることはできませんが、進⾏を遅らせることで、不⾃由なく⽣活を送ること、失明のリスクを減らすことができます。治療⽅法は薬物療法、レーザー治療、⼿術がありますが、緑内障のタイプや、それぞれの患者さんに適した治療を選ぶことが重要です。
基本となるのは点眼薬による治療です。眼圧を下げる点眼薬にはいくつかの種類があり、必要に応じて数種類を組み合わせて使うこともあります。多くの患者さんでよく効きますが、副作⽤で使えない⽅もいます。また、緑内障は⾃覚症状がほとんどないため、きちんと点眼薬をさせない⼈も多く、効率的な治療が期待できないケースも少なくありません。さまざまな観点から点眼薬では治療効果が⼗分でないと判断されたとき、レーザー治療の適⽤が考慮されます。
緑内障の原因の⼀つとして、眼の中の房⽔の出⼝である線維柱帯が⽬詰まりを起こし、房⽔の排出が悪くなり眼圧が上昇することが考えられています。レーザー治療の中に、特殊なレーザーを線維柱帯に照射し、房⽔の排出を改善するものがあります。従来のレーザー治療(ALT:アルゴンレーザー線維柱帯形成術)は線維柱帯の組織にダメージを与えてしまうという⽋点がありましたが、その後登場した新しいレーザー治療(SLT:選択的レーザー線維柱帯形成術)は、線維柱帯には悪影響を及ぼさずに、選択的に狙った細胞のみを照射し、その機能を再活性化することが期待できます。⽇帰りでの外来治療が基本となるSLTは、短時間で終わり痛みや合併症リスクの少ない低侵襲な治療法として注⽬されています。繰り返し治療を受けられるのもメリットです。近年、普及が進みつつあるSLTですが、適⽤となる患者さんでも約2〜3割の⽅には治療効果が⼗分に発揮されず、その原因がまだ明らかでないという⽋点もあります。
点眼薬、レーザー治療でも改善がみられない場合は⼿術が必要です。⼿術にも流出路再建術、線維柱帯切除術などいくつかの術式があります。
もし緑内障になったらどうすればいいですか?
診断と治療の進歩によって、失明の危険性はかなり減らせるようになっています。適切な治療によって⽇常⽣活に⽀障のないレベルを維持している患者さんもたくさんいらっしゃいます。進⾏には個⼈差があり、治療⽅法もいろいろあるので、どの時期にどういう治療を受ければいいのか、信頼できる眼科の医師といっしょに希望を持って治療を続け、⽣涯にわたって「⾒える」を維持していくのが緑内障の治療です。
コロナ禍で、眼科領域でも受診控えが起こっています。緑内障の治療に限らず、これまでうまく病状をコントロールしてきた眼が、定期的な診察・検査を受けないうちに悪くなってしまう例があるのは⾮常に残念なことです。医療機関の多くは、患者さんたちが安⼼して受診できるよう可能な限りの感染予防体制を整えています。感染リスクよりも、⾃⼰判断で治療を中断する不利益の⽅がずっと⼤きいでしょう。現在、何らかの理由で眼の治療を中断してしまっている患者さんは、どうかもう⼀度受診して、あらためて治療を続けてもらいたいと切に願います。
最後に読者へのメッセージをお願いします。
加齢に伴って起こりやすい眼の病気には、眼のかすみや眼の疲れなど、⽼眼と似た症状があらわれるものがあります。⽼眼だと思い込んで放置していると視⼒の低下を招いたり、最悪の場合は失明につながったりするケースもあるので、軽視しないことが⼤切。ふと気付いた「⾒づらさ」や眼の不調を単に「年のせい」とあきらめず、まずは眼科で診てもらうべきです。特に、近くも遠くも⾒づらくなったと感じたのなら、眼の病気の可能性もあるため、視⼒と病気の両⽅をチェックできる眼科へ⾏くのが安⼼です。
緑内障に代表される「⾒る」機能に⼤きなダメージを与える眼疾患の多くは、40歳を境に発症のリスクが⼤きく上昇します。こうした病気から眼を守るため、40歳を超えたら、⾃覚症状がなくても年に⼀度は眼科検診を受けていただきたいと思います。
※文中に記載の組織名・所属・肩書・内容などは、すべて2021年10月時点(インタビュー時点)のものです。
サイトマップはこちら