DOCTOR INTERVIEWドクターインタビュー
- トップページ
- ドクターインタビュー
- 小児科ドクターインタビュー
子どもの未来を
守る砦でありたい
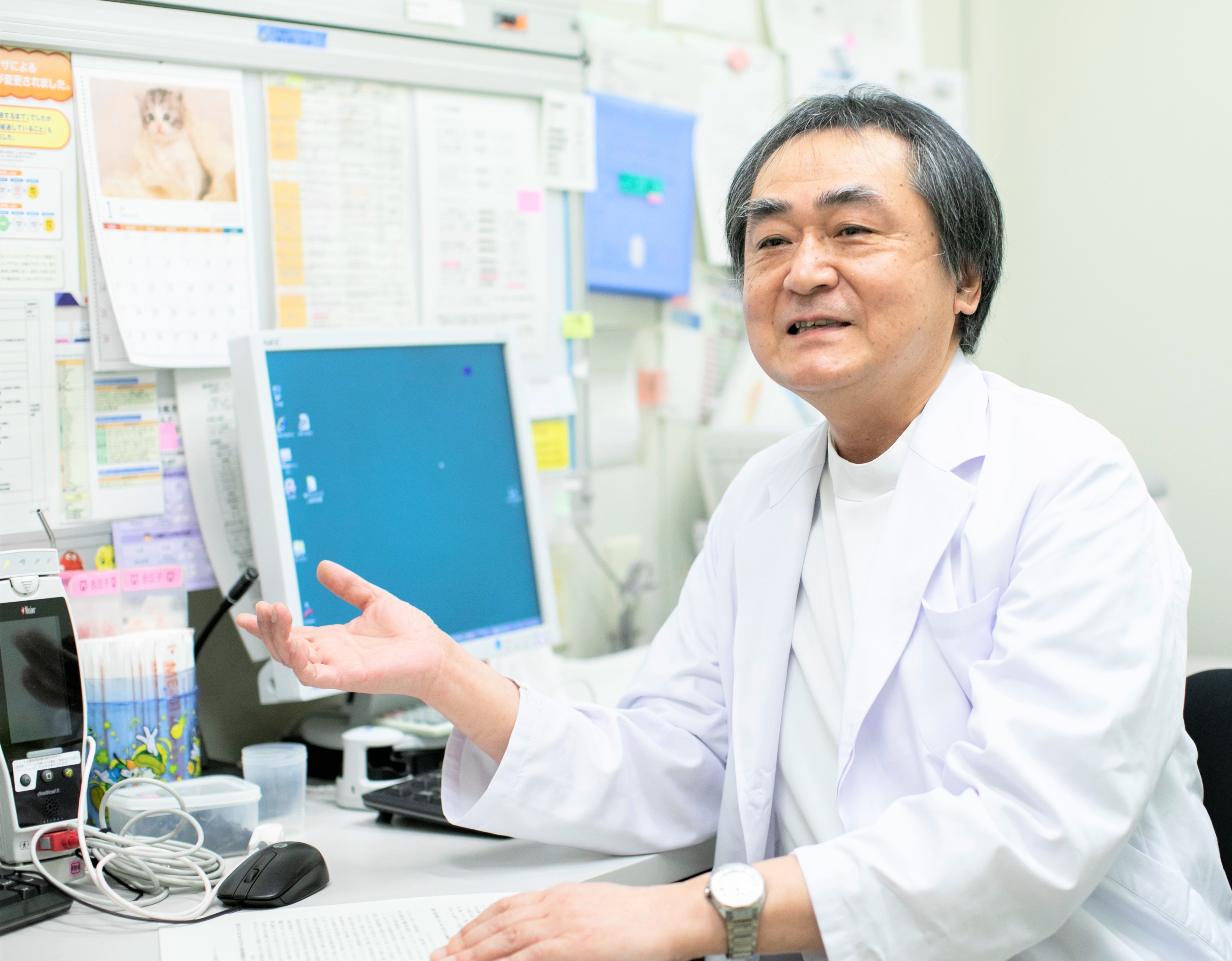
小児科部長 森 俊彦
リスクの高い出産を扱う地域周産期母子医療センターの指定を受け、産婦人科・小児科が緊密な連携を取り、周産期にかかる高度な医療を担っている同院。妊娠から出産、子どもの成長まで切れ目のない専門医療を提供できる体制が整っています。
同院が実践する小児科医療の特色、日々の診療に対する思い、小児科受診のコツなど、約40年にわたり小児科医療の現場で、赤ちゃんと子どもたちの命と成長を見守り支えてきた森俊彦小児科部長(日本小児科学会認定小児科専門医)にお話を伺いました。
どういった診療体制でどんな診療を行っていますか?

札幌市の中核病院の小児科として、新生児から乳児、幼児、学童期、思春期まで、子どもの疾患を幅広く診療しています。医師は常勤医4人、後期研修医2人、非常勤医2人の8人体制(2021.2月現在)です。地域の診療所、クリニックと連携を取りながら、かぜやインフルエンザなど一般的な感染症はもとより、専門的な検査・治療が必要な患者さんを多数受け入れています。当科の方針として、他医療機関より紹介された患者さんをできる限り「断らないこと」を原則としています。至急の入院治療を必要とする患者さんについても、電話交換もしくは小児外来受付から外来担当の医師に直接連絡が入るようになっており、担当の医師は毎朝のカンファレンスで空き病床数を確認しているので、その都度病棟に病床の空き具合を確かめなくても、感染症などで隔離が必要な場合以外は極力すぐに入院を受け入れることができるよう心がけています。
外来診療は、午前に急性疾患主体の一般外来を、午後には心臓、神経、SOTI(食物アレルギー)、アレルギー、腎臓の各分野に豊富な臨床経験を持つ担当の医師による専門外来(完全予約制)を設けています。一般外来では予防接種、乳児健診など地域の保健活動も行っています。また、当科は札幌市の小児二次救急病院として夜間・休日の当番も担当しております。
入院病床は新生児6床と一般乳幼児20床で(2021.2月現在)、入院総数は年間1,200〜1,400名程度です。うちNICU(新生児集中治療室)入院は年間200名前後で、当院で出生した新生児のほか、他の産院からの新生児(低出生体重児、好ビリルビン血症、呼吸障害など)の受け入れも積極的に行っています。重症児は札幌医大病院や北海道立子ども総合医療・療育センター・コドモックルと連携して治療をバックアップする体制が整っています。
専門外来について教えてください。

小児科の医師として全員が小児を総合的に診るジェネラリストとして診療にあたっていますが、専門外来ではそれぞれの医師が心臓や神経、アレルギー、腎臓といった専門分野のサブスペシャリティをもって、特別な検査や治療を必要とする子どもたちを診療します。
医療が進歩して、感染症などの急性疾患、頻度の高い先天性の心疾患など、かつては新生児や乳幼児の命にかかわるような病気も治療ができるようになり、子どもの病気の種類が変わってきました。一方で、食物アレルギーなど、かつてはあまり見られなかった病気にかかる子どもが増えています。
当科でも特に力を入れているのが、SOTI(食物アレルギー)外来です。食物アレルギーとは、本来は体を異物から守る免疫が、特定の食べ物によって体に不利益に働くことをいいます。皮膚のかゆみやじんましん、嘔吐や下痢、呼吸困難など、人によってさまざまな症状が出ます。重症の場合、意識を失ったり、血圧が低下したりするアナフィラキシーショックを起こすこともあります。従来、食物アレルギーと診断されたら、原因となる食物を必要最小限に除去しながら、定期的に医療機関でその食物を食べてみる「食物経口負荷試験」を受けて、食べられるようになっているかを確かめていく、という治療法が基本でした。近年、さまざまな研究から完全除去を続けるより、少量でも食べていく方が食べられる範囲を広げていける可能性が高いことが分かってきました。負荷試験を行って限界量を調べ、厳密に摂取量を計算して計画的に耐性獲得を目指すという新しい治療法(経口免疫療法)も登場しています。今後、学校給食などで食べ物(食材)の制限を余儀なくされていたお子さんの負担が軽減されることも期待できます。
専門外来は設けていませんが、お子さんの身長の伸びが気になる場合の成長ホルモン治療、生後間もない赤ちゃんの体にできる乳児血管腫(いちご状血管腫)に対する内科的治療(薬物療法)も積極的に行っています。
どういうことを心掛けて診療にあたっていますか?

小児を診察する上で重要なのは、年齢に応じた診察が必要なことです。例えば、乳児は自分で症状を訴えられませんし、詳しい神経学的な所見を得ることも難しいです。啼泣が激しい時は、心肺や腹部の十分な所見を得られないこともあります。ですから、小さなお子さんの場合は、個々の所見というよりも、全身の様子や動き方を診ることが大切です。発熱、せき、鼻汁、下痢、嘔吐などの症状と、呼吸がはやい、顔色がよくない、体の動きの左右差、泣き方の様子といった全身の状態から総合的に判断し、緊急性や入院の必要性などを慎重に見極めていきます。保護者の皆さんから伝えられる情報も大きなヒントになります。「何か気になることはありますか?」とお聞きした時、「ささいなことかもしれませんが、実は…」と語られる内容に、病気の診断や鑑別にとても重要なことが含まれているケースも多いです。
小児科の医師は「子どもが好き」「子どもを助けたい」などの動機に支えられている面が多く、それだから皆、大変でも続けていけるのだと思います。私自身は、治療して元気になった子どもたちの姿や笑顔を見るのが最大のやりがいとなっています。
小児科受診のコツを教えてください。
病院を受診するかどうか、一番の決め手になるのはお子さんが「元気か、元気でないか」です。たとえ発熱やせきがあっても、元気があり食欲もあれば大抵の場合、心配はいりません。保護者の皆さんの「いつもと違う」という第一印象、直感がとても重要です。熱がそれほど高くなくても、いつもと違って元気がなく、ぐったりしているようならすぐに受診してください。普段のお子さんの状態をよく知り、不測の事態に備えることが大切です。
新たな取り組みなど、今後の展望をお聞かせください。

社会構造の変化で、心の問題や精神科的な疾患、特に発達障害や自閉症スペクトラム、不登校のお子さんが以前に比べて増えていることも、最近の特徴として挙げられます。日本では児童精神を専門に診察する医師が少なく、子どもたちが心に問題を抱えていても、早期に適切な支援を受ける仕組みが不足しています。今後さらに需要が増していく児童精神の専門外来を、近い将来、当科に開設したいと考えています。
もう一つは、医療的ケアが必要なお子さんのご家族が、外出や休息、その他養育ができない期間をサポートする目的で、お子さんを一時的に預かるレスパイト入院という医療サービスの導入も果たしたいです。
広大な北海道には21の医療圏がありますが、医療資源の多くは札幌に集中しています。小児科においても同様で、札幌市とそれ以外の地域では医療提供体制に差があります。地域格差を解消し、平等に医療を受けられる環境をつくっていくのは北海道の医療の大きな課題ですが、今、当科ができるのは、札幌市内外はもとより道内各地、遠方から紹介される患者さんを可能な限り断らないという信念を持ち続け、それを実践していくことです。「北海道の小児医療を守る砦」という気概を持って、誰もが安心して出産し、出産後も安心して育児ができる社会をつくる一助になれるよう、スタッフ一丸となって前進していきます。
最後に読者へメッセージをお願いします。
新型コロナウイルス感染症については、子どもは感染しても発症しないか、発症しても軽症であるケースが比較的多いようです。また、子どもだけのクラスター報告は全体の中では非常に少ないです。油断は禁物ですが、必要以上に恐れるのではなく、「正しく恐れる」心構えをもって、コロナ禍を共に乗り越えていきましょう。マスク着用や手洗い、うがいの励行、3密を避けるなどの感染予防対策により、新型コロナウイルス感染症以外の感染症が激減しています。今後も現在行っているコロナ対策を続けていけば、いわゆる感冒といわれる感染症の大きな流行は抑えられることを示しているのだと思います。
心配なのは、新型コロナウイルス感染症への感染を心配して、他の病気の予防接種や健診の受診率が下がっていることです。予防接種や健診は不要不急ではなく、子どもたちにとって必要で後回しにはできないものだということを強く訴えたいです。
予防接種について、最後にもう一つお話します。近年、乳児が感染すると死亡する恐れもある百日せきの患者さんが増え続けています。百日せきは急性の気道感染症で、せきやくしゃみで感染します。せき発作に加え、息を吸う時に笛のような「ヒュー」という音が鳴るのが特徴です。特に、生後6カ月未満の乳児が発症すると呼吸困難になるなど重症化する危険性が高いです。ワクチンは定期接種の対象(4種混合ワクチン)となっており、予防のためにはワクチン接種が重要なのですが、ワクチンの免疫効果は4~12年で減弱するため、10歳以上の子どもや大人が再感染することがあります。実際に、予防接種の効果が消失した年長児や大人の再感染者が増え、このような既接種の感染者からワクチン未接種の乳幼児などへ感染するケースが目立っています。先進国で百日せきワクチンの接種を学童期に行っていないのは日本だけです。小児科医と相談し、小学校入学前に追加の任意接種を受けることをお勧めします。
※文中に記載の組織名・所属・肩書・内容などは、すべて2021年1月時点(インタビュー時点)のものです。
サイトマップはこちら

